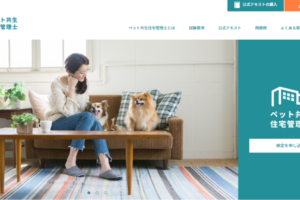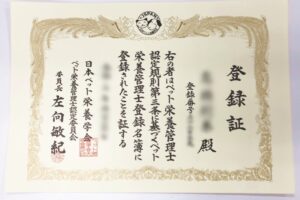猫の肝臓の働き
肝臓は、猫の体の臓器の中で最も大きい臓器で、栄養の分解や合成、貯蔵、そして体内の毒素を無毒化するなど様々な仕事をこなしています。
- 栄養を分解
- 体に必要な栄養に再合成
- 栄養を貯蔵
- 毒素を解毒化
猫は他の動物よりタンパク質の要求量が多く、タンパク質は肝臓にある酵素で分解されます。また、体内でタンパク質が分解される時に毒素(アンモニア)を生成させるので、猫の体内では通常より多くのアンモニアが生成されます。このため解毒を行う肝臓は猫にとって特に重要な器官になると言えます。
猫の肝臓病とは
肝臓病は、肝疾患や病気の総称で、肝臓に炎症や異常が出ることで、肝機能が正常に働いていない状態です。
体積が大きく栄養蓄積も行う肝臓は予備能力や再生能力が非常に高いため、多少のダメージでは症状や痛みとして表れません。
このことから肝臓は「沈黙の臓器」とも言われますが、症状が出る頃には肝臓病がかなり進行してしまっていることが多いため、定期検診をしたり適切な食事管理で予防するなどが必要な臓器です。
猫の肝臓病の症状
初期症状
初期は肝臓による症状かどうかわかりにくく、ただの体調不良と勘違いしてしまうことも多いです。
- 食欲がなくなる
- 嘔吐・下痢
- 動きが悪くなる
- 元気がなくなる
- お腹を触られるのを嫌がる
- 目や歯茎に黄疸が現れる
末期症状
末期になると肝臓で行われるアンモニアの解毒や栄養の合成、分解などが正常に行われなくなり、肝性腹水や肝性脳症のようなより深刻な症状が併発します。
- 体重が減少
- 食欲がなくなる
- 腹水(お腹に水が溜まる)
- 肝性脳症(痙攣・てんかん・昏睡状態)
- しっかり歩けない
猫がかかりやすい肝臓病
急性肝炎(ウイルス性肝炎)
急性肝炎はウイルスや細菌、寄生虫などが原因で肝臓が炎症を起こす肝臓病です。猫エイズや伝染病などの、感染症による症状の一つとして肝炎にかかることもあります。重症の急性肝炎は緊急性が高く、一刻も早い治療が必要になりますが、適切な治療をすれば完治も可能です。
慢性肝炎
慢性肝炎は一時的ではなく長期にわたって肝臓の炎症が続く病気で、免疫力が下がっていたり長期的に肝臓の炎症が続くことが原因と考えられています。原因ははっきりとはわかっていませんが、末期になると肝細胞が破壊と再生を繰り返すことで繊維化する肝硬変という病気に発展します。
肝硬変
肝硬変は猫の肝臓組織が何度もダメージを受けて破壊と再生を繰り返し、肝臓組織が固く繊維化してしまう病気です。一度繊維化した組織は元に戻ることはないので、肝臓機能も落ちたままです。このため肝硬変になったら、これ以上進行しないよう残りの肝臓組織を守る治療や、機能が落ちた肝臓に負担をかけない食事管理を行います。
門脈体循環シャント
門脈シャント(門脈体循環シャント)とは、毒素を肝臓へと運ぶ血管「門脈」が、異常血管の形成によって静脈の血管とつながってしまい、毒素が全身に流れてしまう病気です。先天性のものと後天性のものがありますが、門脈シャントは遺伝が原因の先天性のものが多いですが、治療によって軽減や回復が可能です。
肝リピドーシス
肝リピドーシスは肥満猫に多い病気で、肝臓に脂質が溜まり過ぎることで起こる肝臓病で、中年~老齢猫もかかりやすいです。肝リピドーシスは大きなストレスなどでも発症することがあるため、環境が大きく変わった時や猫がストレスを感じて塞ぎ込んでいる時は気を付けましょう。
肝臓癌
肝臓に腫瘍ができる病気で、寿命が延びたため、癌の発生も徐々に増えてきています。肝臓癌は中高齢期に発症することが多く、他の癌治療と同じような外科手術による摘出や抗がん剤治療などを行います。
猫の肝臓病の治療方法
肝臓病の検査
肝臓病の症状は見ただけではわかりにくいですが、肝臓病は健康診断などで行われる血液検査で確かめることができます。
肝臓病の治療
肝臓病になった原因や症状、病名によって治療方法は変わってきますが、基本的には猫に起こっている症状に応じた抗生物質を投与して、猫の症状を抑える治療と食事による療法が治療のメインとなります。
ただし門脈体循環シャントや肝臓癌の場合は、外科手術などの治療が行われる場合もあります。
肝臓病になった猫の食事療法
重症ならタンパク質を制限して糖質で補う
肝臓病がかなり進行している場合、食事療法ではタンパク質の量を制限し、代わりに糖質(炭水化物)を与えます。糖質は猫にとって効率良く分解できる成分ではありませんが、猫も摂取した糖質の30~40%はエネルギーとして利用することができるので、一時的にタンパク質の代替となるエネルギー源として与えます。
軽症なら制限しない場合も
糖質は分解される際にアンモニア(毒素)を作らないため、肝臓への負担を軽減できます。ただし肝臓病が初期の場合には、肝臓の回復のためにタンパク質を多く摂取した方がいいので、タンパク質制限をするかどうかの判断は獣医さんの指示の元で行います。
猫の肝臓病の予防方法
猫の肝臓病は年齢を重ねることで発症しやすくなる病気もあるため、完全に予防するのは難しい病気ですが、なるべく猫が肝臓病にならないよう、下記のような食生活や栄養バランス、運動量などに注意しましょう。
運動やカロリー制限で肥満予防
肝リピドーシスなどの肝臓病は肥満が原因です。このため日頃から運動をさせたりカロリー制限をしたキャットフードを与えるなど体重管理を行いましょう。
屋内飼育と予防接種
またウイルスや細菌感染、他の感染症の症状として肝臓病になることもあります。猫を完全に室内で飼うことや予防摂取を受けさせることも予防策の一つになります。
定期的な健康診断
さらに肝臓病は血液検査で発見できるため、健康診断で肝機能が落ちているかどうかも知ることができます。そのため健康診断は必ず定期的に受けるべきです。
細菌は肝機能をサポートする猫用のサプリメントも登場しているためチェックしてみてもいいのではないでしょうか。
肝機能を助けるサプリ
肝機能を助けるビタミンは食事やサプリから摂取できるよう日頃から栄養管理することも大切です。総合栄養食を与えていれば基本的に栄養素に過不足が出ることはありませんが、肝機能が元々低い猫の場合はそれを獣医師やペット栄養管理士に相談の上、サプリメントなどを利用してもいいかもしれません。