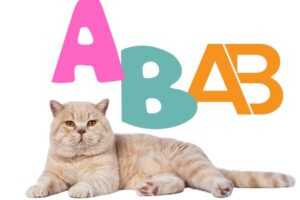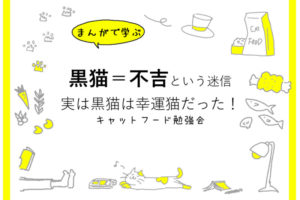その症状、膀胱炎の可能性がありますね。
実は、猫の膀胱炎の多くは”突発性膀胱炎”といって、細菌ではなく生活環境やストレスが関係していることもあります。しかも、膀胱炎は一度治っても再発しやすい病気なんです。
今回は、猫の膀胱炎の特徴や原因、飼い主ができる対策を解説していきます。
猫の膀胱炎の特徴
猫の膀胱炎は泌尿器疾患の一つで、膀胱の内側に炎症が起こる病気です。
とくにオスはメスよりも尿道が細く長いために詰まりやすく、重症化しやすい傾向にあります。放置すると尿がまったく出なくなり、急性腎不全や命に関わる状態に進行することもあります。
猫の膀胱炎の症状
猫の膀胱炎でよく見られる主な症状は下記のとおりです。
- トイレに何度も行くのに、尿の量が少ない
- 排尿時に鳴く・痛がる様子を見せる
- おしっこの色が濃い、または血が混じる(血尿)
- トイレ以外の場所で排尿してしまう
- トイレで長く座り込む、落ち着かない
- 尿がまったく出ない(尿道閉塞の可能性)
- 排尿後に頻繁に陰部をなめる
- 尿の臭いが強い、または異常に少ない
- 食欲の低下、元気がない、動きが鈍くなる
- 鳴き声が増える、イライラするなどの行動変化
これらのうち、とくに「尿が出ない」「血が混じる」などの症状が見られる場合は急を要する可能性があるため、早急に動物病院を受診することが大切です。
猫の膀胱炎の原因
ストレスと水分不足
猫の膀胱炎の多くは「特発性膀胱炎」と呼ばれ、明確な原因が特定できないケースが多いのが現状です。しかし、その背景にはストレスや水分不足が大きく関係していると考えられています。
環境の変化、トイレの場所・形・匂い、同居動物との関係など猫はわずかなストレスでも膀胱の神経バランスを崩しやすく、炎症を引き起こすことがあります。
加えて、飲水量が少ないと尿が濃くなり、膀胱内の細菌や結晶が増え、炎症の引き金となります。室内飼いの猫は運動量が少なく、水をあまり飲まない傾向があるため、とくに注意が必要です。
細菌感染
細菌感染が原因となる膀胱炎もあります。
高齢猫や免疫力が低下している猫、糖尿病などの持病を持つ猫では細菌が尿道から膀胱内に侵入しやすくなります。感染性の膀胱炎は発熱や血尿、悪臭のある尿を伴うこともあり、抗菌薬による治療が必要です。放置すると腎臓にまで炎症が広がる可能性もあるため、早期の受診が欠かせません。
尿結石や尿道閉塞
膀胱炎のような症状が見られる場合、尿路結石も考えられます。
尿に含まれるミネラルが結晶化し、膀胱や尿道に小さな石を作ると、排尿が困難になります。とくにオス猫は尿道が細く長いため、結石が詰まりやすい傾向にあります。トイレで何度も踏ん張るのに尿が出ない、尿の色が濃い・赤い場合はすぐに動物病院へ行くことが重要です。
完全に詰まると急激に腎臓へ負担がかかり、数日で命に関わる危険性があります。
飼い主ができる予防策
膀胱炎は一度治っても再発しやすい病気であるため、日頃から膀胱炎にならないような予防策を取ることが大切となります。
水分の摂取量を増やす
猫の膀胱炎を防ぐためには、まず水分摂取量を増やすことが大切です。
常に新鮮な水を複数の場所に設置し、流れる水を好む猫には循環式の給水器を導入するのがおすすめです。ウェットフードを取り入れて自然に水分を摂らせるのも良いでしょう。
トイレを清潔に保つ
トイレ環境の清潔さと静けさを保つことも重要です。
汚れた砂や狭いトイレは猫にストレスを与え、排尿を我慢する原因となります。猫の数+1個のトイレを用意し、日々の清掃を怠らないようにしましょう。
ストレスの軽減
生活環境のストレス軽減も欠かせません。急な模様替えや来客、他の動物との接触など、猫にとって不安要素やストレス要因を減らす工夫をしましょう。
膀胱炎のサインを見逃さない
猫は痛みを隠す動物です。膀胱炎の初期は、トイレ以外でおしっこをしたり、長く座り込む、鳴きながらトイレに行くなどのわずかなサインしか出さないこともあります。
普段から尿の回数・量・色を観察し、少しでも異常を感じたらすぐに受診することが、早期発見と再発防止につながります。とくに「おしっこが少ない」「トイレで踏ん張る」「血が混じっている」といった症状が見られた場合は、自己判断せず動物病院へ行きましょう。
まとめ
- 膀胱炎は泌尿器疾患の一つで、排尿異常や痛みを伴う病気
- 主な原因はストレスや水分不足で、特発性膀胱炎が多く見られる
- オスは尿道が細く、尿詰まりを起こしやすいためとくに注意が必要
- 予防には新鮮な水の確保、清潔なトイレ環境、ストレス軽減が重要
- 膀胱炎は再発しやすいため、日常の観察と尿検査が欠かせない