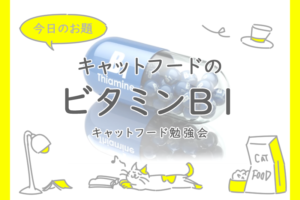キャットフードを混ぜるのはNG!
フードローテーションであればOK
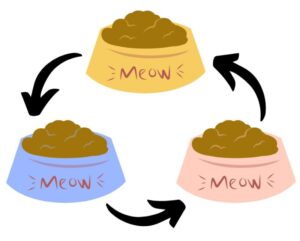
フードローテーションのように、目的があってキャットフードを混ぜる(切り替える)のは問題ありません。しかし、キャットフードを混ぜたからといって両方の効果を得ることができるわけではないため、複数のキャットフードを日常的・長期的に与えることはおすすめできません。
キャットフードはそれぞれメーカーが味や栄養バランスを考えてレシピを作り、製造をしています。そのため、総合栄養食であるキャットフードをきちんと食べさせていれば栄養が偏ることがなく、健康に問題はありません。
しかし、複数のキャットフードを混ぜたものを日常的・長期的に与えている場合、栄養に偏りが出てしまい猫にとって必要な栄養が足りなくなる恐れがあります。
混ぜるメリットもある
複数のキャットフードを混ぜることのメリットもあります。
- キャットフードの飽き防止
- 食べなくなるリスクが軽減 など
ただし、これらの利点を最大限に活用するためには、猫の健康状態や栄養の必要性を考慮しつつ、適切に行わなければなりません。
なぜ混ぜてはいけない?健康への影響について
混ぜても両方の効果を得ることはできない
複数のキャットフードを混ぜて与えたからといって、両方の栄養を十分に得ることができるわけではありません。栄養が過剰または不足する可能性があります。
例えば、ヘアボール排出タイプのキャットフードと肥満対策のキャットフードがあるとします。
ヘアボール排出タイプのキャットフードは食物繊維が10%近く入っていると思いますが、たんぱく質や脂質は抑える必要はありません。食物繊維が多くなった分、肉類の含有量が減って結果的にたんぱく質や脂質が減っている場合はあります。
反対に肥満対策タイプのキャットフードは主に脂質、次にたんぱく質を減らして、健康に害がないように作られています。必要最低限を摂取し、健康的に痩せていくことを目指すことから与える量も重要です。腸内環境改善のために食物繊維は少し多めに含まれている場合はあります。
こうした2つを混ぜて与えた場合、肥満対策で減らした脂質やたんぱく質はヘアボール排出タイプのフードで補われてしまうことになり、全く意味がありません。また、混ぜたことで相対的に食物繊維量が減ってしまっては、ヘアボール対策を利用している意味がなくなってしまいます。
また、栄養バランスも崩れてしまう可能性が高く、猫にとっては効果も出ない上に栄養もきちんと摂取できず、いいことがないという結果にもなりかねません。
アレルギーが特定できない
複数のキャットフードを混ぜることで、どのフードが猫に合っているか、あるいは合わないかを判断するのが難しくなります。
例えば猫がキャットフードを食べたあとにアレルギーを起こした場合、どちらのキャットフードが原因なのか特定しづらくなります。これにより食事の調整が非常に難しく、猫の健康に悪影響を及ぼすリスクが高まります。
味覚の混乱
複数のキャットフードを混ぜるとそれぞれの風味や食感が混ざり、キャットフードへの嗜好性が上がることもありますが、反対に嗜好性を失う可能性があります。
猫は非常に味に敏感な動物であり、一度気に入らないキャットフードと認識すると、その後のキャットフード全般に対する興味を失う可能性があります。
開封から消費までの期間が長くなる
複数のキャットフードを混ぜて与えることで、1種類のみを与えている場合に比べて開封から使い切るまでの期間が長くなります。
とくに日本は高温多湿の環境なので、通常キャットフードの開封後は1ヶ月程度で使い切るのがベストです。しかし複数のキャットフードを開封することで使い切るまでの期間が長くなり、風味が落ちたり、酸化やカビ発生などのリスクも高まります。
まずは獣医師・栄養士に相談を
複数のキャットフードを混ぜて与えたい場合は、獣医師や栄養士に相談しましょう。
複数のキャットフードを混ぜるメリットもあるため、メリットやデメリットをきちんと確認し対策をすることが大切です。とくに成長期の子猫や病気を抱える猫の場合、食事が健康に直結するため、慎重な管理が必要です。
まとめ
- 複数のキャットフードを混ぜたものを日常的・長期的に与えるのはNG
- フードローテーションが目的であればOK
- ドライフードとウェットフードはOK(ただし日常的・長期的はNG)
- 複数のキャットフードを混ぜたものを与えたい場合はまず獣医師に相談