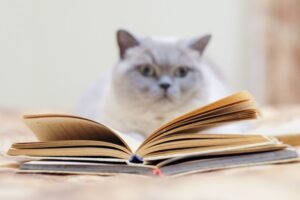今回は猫との引っ越しにおいてするべきことや、ストレスを感じさせない方法や注意点について、引っ越し前、引っ越し当日、引っ越し後に分けて解説します。
引っ越し前にすること
- ペット可の物件を探す
- 引っ越し先の動物病院を確認
- 首輪や迷子札、マイクロチップを付ける
- 家具や猫砂は買い換えない
- クレートに慣れさせる
- 移動で飛行機を使う場合は早めに確認・予約
- 書類の提出や手続き
①ペット可の物件を探す
引っ越しが決まったら物件探しからスタートですが、必ずペット可の物件を選びましょう。当たり前と感じるかもしれませんが、「バレなければ大丈夫」「迷惑をかけないようしつける」「急遽飼うことになった」といった理由で、ペット不可の物件で犬や猫を飼っている方は意外と多いのです。
トラブルとなって退去せざるを得ない状況になる可能性もあるため、早めの情報収集と準備が重要となります。
②引っ越し先の動物病院を確認
引っ越し先の地域にある動物病院の位置を確認しておきましょう。引っ越しによるストレスで猫が体調不良になる恐れもあるため、2か所程度はあらかじめ確認しておくと安心です。
③家具や猫砂は買い換えない
猫は環境の変化に敏感であるため、匂いや馴染みのあるものに安心感を得やすい動物です。家具に残っている猫自身の匂いによって新居を「自分の場所」と感じることができ、ストレスを軽減してくれるでしょう。
特に猫が普段使用しているベッドやキャットタワーなどの家具や、使い慣れた猫砂は引っ越し先でも使用することがおすすめです。新しい家具の購入を検討している場合は、引っ越し直後ではなく、猫が新居に慣れてから購入するのが理想的です。
④首輪や迷子札、マイクロチップを付ける
猫は大きな不安や警戒心、ストレスによって外に飛び出したり脱走しやすい傾向にあります。特に引っ越し作業中はドアや窓が開けっぱなしの場合が多く、また引っ越し業者や管理会社、設備の点検などで見慣れない人に警戒してストレスとなります。
引っ越し前に、万が一のために首輪や迷子札、マイクロチップの装着をおすすめします。
⑤クレートに慣れさせる
猫は見慣れない空間や閉じ込められる状況に強い警戒心や不安感を抱きやすく、また過去に動物病院への移動などネガティブな経験と結び付いていることが多いため、クレート(キャリーケース)を嫌がる傾向にあります。
クレートに慣れるには時間がかかるため、引っ越しの数週間前から準備を始めましょう。急に閉じ込めるのではなく、クレートを普段の生活空間に置いて、猫が自由に出入りできる状態にしておきます。クレートの中に猫の好きなタオルや毛布を敷いたり、おやつを入れて楽しい体験と関連付けることで、クレートが生活の一部として安心感を得ることができます。
⑥移動手段の確認・予約
引っ越し先までどのように移動するかを事前に把握しましょう。
・車
猫にとって一番安全でストレスを感じさせない移動手段は車です。車を所有していない場合はレンタカーやタクシーを検討しましょう。引っ越し当日までにルートや休憩場所などを確認して、スムーズに引っ越し先まで行くことが大切です。
・電車、バス
移動手段が電車やバスの場合は、事前にペットの取り扱い規約や手順を確認しましょう。
・飛行機
飛行機で移動する場合、国際航空運送協会(IATA)の基準を満たすクレートや、健康診断書や予防接種証明書が必要となる場合があるため、早めに問い合わせをして事前予約をしなければなりません。
犬においては、夏季期間においてブルドッグやボストンテリアなどの短頭種の預かりを中止している場合があります。猫についての預かり中止の記載はありませんが、エキゾチックショートヘアやブリティッシュショートヘア、ペルシャなどの鼻が低く、顔が平らな猫種は熱中症や呼吸困難を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。
猫が呼吸器や循環器に病気がある場合は、引っ越し前にかかりつけ獣医師に相談しましょう。
・ペット引っ越しサービスを利用する
飛行機での移動が不安な場合は、ペット引っ越しサービスを利用するのも良いでしょう。
ペット引っ越しサービスとは、猫にストレスを感じさせずに安全に移動できるよう配慮され、サービスによっては空港での手続きの代行や輸送手段を行ってくれます。
距離やサービス内容によりますが、費用は数万円~数十万円程度。利用する場合は早めに予約をしましょう。
⑦書類の提出や手続き
犬の場合は法律で登録が義務付けられているので、市町村の役所で登録住所の変更が必要ですが、猫は登録が義務付けられていないため、役所で行う手続きは特にありません。しかし自治体によっては必要となる場合もあるので、確認しておきましょう。
マイクロチップを装着している場合は、引っ越し後に手続きが必要となります。手続きし忘れに注意しましょう。
引っ越し当日にすること
- 食事は移動の2~3時間前に済ませる
- 車での移動:定期的に休憩と水分補給
- 公共交通機関での移動:混雑を避ける
- 飛行機での移動:時間を要するため早めに到着
- 引っ越し作業前:猫を部屋に隔離する
- 引っ越し作業中:定期的に様子を見る
- 猫用品はすぐに取り出せる場所に置く
①食事は移動の2~3時間前に済ませる
移動中の車酔いを防ぐため、食事は移動の2~3時間前に済ませましょう。
しかし満腹状態での移動は吐き気や不快感を引き起こす可能性があるため、いつもの食事より少なめの量を与え、移動中に適宜おやつを与えるのがおすすめです。
②車での移動:定期的に休憩と水分補給
車での移動は家族だけの空間であり、また定期的に休憩時間を確保してトイレやリフレッシュの時間を作ることができるため、他の移動手段と比べてストレスを感じにくいでしょう。
急ブレーキやカーブなどの揺れを防ぐため、クレートやキャリーケースはシートベルトで固定しましょう。
また毛布やブランケットでクレートを覆うこともおすすめです。クレートを暗くすることで周囲の視覚的な刺激や騒音、人や車の動きを減らすことができ、猫にとって安全な隠れ場所のような感覚となって落ち着きやすくなります。
逆に、毛布をかぶせることで不安を感じる猫もいるため様子を確認しながら調整してください。
③公共交通機関での移動:混雑を避ける
電車やバスで移動する場合、猫の安全と快適さを確保しつつ、周囲の人に配慮することが重要です。
キャリーケースはドアがしっかりと閉じられる安全なものを選び、中に毛布やタオルを入れて快適さを確保しましょう。キャリーケースをしっかり手に持ち、揺れや衝撃を吸収します。床に置く場合は、すべらないよう注意しましょう。
通勤通学で混雑が予想される朝と夕方の時間帯は避け、車両の端や空いている場所を選ぶことで、猫と周囲の人のストレスを減らせます。またキャリーケースに毛布をかけて外部の刺激を遮断すると、猫が落ち着きやすくなります。
④飛行機での移動:時間を要するため早めに到着
ペットの搭乗手続きには時間がかかるため、早めに空港に到着しましょう。専用のカウンターで手続きを行います。
フライト中、猫が過ごす貨物室内の温度や気圧はペットに対応した環境が保たれていますが、フライト前に再確認しておくと安心です。
到着後すぐに猫の健康状態を確認し、緊張や疲れがみられる場合は静かな環境で休ませましょう。
⑤引っ越し作業前:猫を部屋に隔離する
引っ越し業者や設備の点検などで人の出入りが多い時間帯は、目を離したスキに脱走してしまう恐れがあります。またストレスや疲れで警戒心が強くなっているため、外に逃げるように飛び出してしまうこともあります。
引っ越し作業をする前に、猫が玄関や窓から脱走するのを防ぐために、猫をクレートに入れたり静かな部屋で隔離しましょう。ドアに「猫がいるので開けないでください」などと張り紙して、引っ越し業者の方に伝えておくのも良いですね。
⑥引っ越し作業中:定期的に様子を見る
作業に夢中になってしまいがちですが、猫を長時間放置せずに定期的に様子を確認しましょう。猫がずっと鳴いていたり、過剰な舐め行動などの不安行動をしている場合は多大なストレスを感じている要因なので、優しく声をかけたり、数分だけでも寄り添ってあげましょう。
可能であれば、引っ越し作業中はペットシッターや家族に預けることもおすすめです。
⑦猫用品はすぐに取り出せる場所に置く
引っ越しによる猫のストレスを取り除いて安心してあげられるよう、猫用品が入った段ボールはすぐに取り出せる場所に置きましょう。
猫用品が入った段ボールが他の段ボールに埋もれている場合、すぐにタオルやおやつを取り出すことが難しくなってしまいます。
引っ越し後にすること
- 猫が隠れる場所を作る
- 自由に探検してもらう
- 食事のルーティンを維持
- ストレスサインの観察
①猫が隠れる場所を作る
猫は緊張状態が続くと体調を崩してしまう恐れがあるため、猫が安心できるような隠れる場所を作ってあげましょう。猫は暗くて狭い場所や高い場所を好みます。
②自由に探検してもらう
猫が安心できる隠れる場所を確保したら、自由に部屋を探検させてあげましょう。
最初は1つの部屋にトイレ、ベッド、食器など普段使い慣れたアイテムを配置し、猫が安心して過ごせる環境を作ります。猫がリラックスしている様子を確認しながら、少しずつ探索範囲を広げていきます。
警戒心が強い猫や臆病な猫はキャリーケースから一歩も出てこない場合もありますが、無理に歩かせるようなことはしないようにしましょう。
③食事のルーティンを維持
引っ越し前と同じタイミングで食事を与えて一貫性を保つことで、猫のストレスを軽減できます。
また、引っ越しの荷ほどきに夢中になりすぎず、猫と遊ぶ時間は必ず作ることで新しい環境に対するポジティブな印象を与えることができます。
④ストレスサインの観察
猫が下記のような行動を示した場合、ストレスを抱えている可能性があります。
- 食欲不振
- トイレの失敗
- 過剰に鳴く
- 過剰に毛づくろいをする
- 家具やおもちゃを噛む
引っ越しから一週間は特に注意深く猫の行動を観察し、食事量や排泄回数を記録しましょう。ストレスが数週間以上も続く場合は動物病院で診てもらってください。
まとめ
- 引っ越し前に慣れ準備や移動の手配、マイクロチップなどの準備が必要
- 移動の2~3時間前に食事を済ませる
- 引っ越し作業中はクレートに入れたり、部屋に隔離する
- 引っ越し後は猫のストレスサインを見逃さない