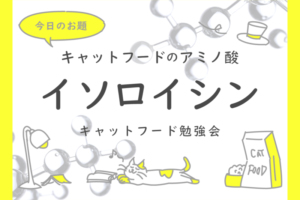それは“好き嫌い”による行動と考えられますね。猫は嗅覚や味覚、食感の好みがとてもはっきりしているので、気に入らないキャットフードにはわかりやすく反応します。
キャットフードを好き嫌いする背景には、猫特有の味覚や嗅覚、学習の影響などいくつかの理由が関わっています。
今回は猫がキャットフードを好き嫌いする理由やリスク、飼い主さんができる工夫を解説します。
「好き嫌い」と「食べない」の違いは?
キャットフードの「好き嫌い」と「食べない」は似ているようで、実は意味合いが違います。
「キャットフードの好き嫌い」とは
これは、嗜好や経験に基づく持続的な傾向を意味します。好き嫌いの場合は、下記のような行動や仕草を示します。
- 匂いを嗅いで立ち去る
- 口に入れてもすぐ吐き出す
- 一部だけを食べる
- フードボウルの前で鳴く
- 食べるまで時間がかかる
好き嫌いは病気ではなく、猫の性質・学習・味覚嗜好の違いが原因であることが多いです。とくに成猫や高齢猫の場合は好き嫌いを治すには時間がかかり、根気が必要となりますが、治すことができます。
「キャットフードを食べない」とは
これは、一時的・突発的にキャットフードを口にしない状態を指すことが多いです。
- 体調不良や病気で食欲そのものが落ちている
- キャットフードが酸化・劣化して匂いが変わっている
- 環境の変化やストレスで食べない
つまり、「食べない」は健康問題や環境要因による可能性が高く、注意深く観察・対応する必要があります。
猫がキャットフードを好き嫌いする理由
猫がキャットフードを好き嫌いする理由は下記の5つが考えられます。
- 味覚による影響
- 嗅覚と鮮度の問題
- 食感や粒の大きさ
- 過去の経験や学習
- 環境や心理的な要因
①味覚による影響
猫は人間や犬よりも味蕾(味を感じる器官)が少なく、とくに甘味を感じ取ることができません。これは、進化の過程で肉食に特化した結果、甘味受容体を失ったためです。
そのため、猫にとってキャットフードの甘みは魅力的ではなく、肉や魚に含まれるアミノ酸由来の旨味成分に食欲が刺激されます。香りや弱く、油分が少ないキャットフードは好まれにくい傾向があります。
②嗅覚と鮮度の問題
猫は嗅覚が人間の数倍も敏感で、キャットフードの匂いの違いを鋭く嗅ぎ分けます。開封して時間が経ったフードや、保存状態が悪く油脂が酸化したフードは、人間には分からなくても猫には不快な臭いとして感じられます。その結果、「これは危険なもの」「食べたくない」という行動につながります。
猫がキャットフードを食べないと感じたとき、実は保存方法や鮮度の低下が原因であることも多く見られます。
③食感や粒の大きさ
キャットフードの粒が硬すぎたり大きすぎたりすると、猫は噛みにくさや違和感を覚えて避けることがあります。逆に、柔らかく小さな粒を好む猫もいます。
このように食感や粒のサイズの違いが、キャットフードの好き嫌いを左右する大きな要素となります。
④過去の経験や学習
過去に、キャットフードを食べたあとに吐いたり下痢をしたりという経験をすると、猫はそのその記憶と匂いが結びつき、キャットフードを「危険な食べ物」と学習して避けるようになります。キャットフードそのものが原因でない場合も、体調不良と結びついた記憶が偏食を強めてしまうこともあります。
また、好き嫌いをするのは子猫時代の食事が関係していることもあります。子猫の時に食べたものは安全で食べられるものと記憶されるため、小さいときから色々な味のキャットフードを食べさせることで、好き嫌いを少なくすることができます。
⑤環境や心理的な要因
食器の素材や置き場所、周囲の環境も重要となります。騒がしい場所で食事をすると落ち着かず、食欲を示さないこともあるため、安心して食べられる環境を整えることも忘れてはいけません。
飼い主ができる工夫と改善方法
フード切り替えのコツ
猫がキャットフードを食べないときは、別のキャットフードを与えてみましょう。
ただし、キャットフードを切り替えるときはすぐに変えるのではなく、少量ずつ混ぜながら数日から数週間かけて切り替える方法(フードローテーション)が、偏食を避けつつ受け入れやすくするポイントです。
香りや温度を工夫する
ウェットフードを軽く温めて香りを引き立てたり、ドライフードにぬるま湯をかけて風味を増すことでキャットフードへの興味が増し、食欲が戻ることもあります。
まとめ
- 猫の好き嫌いは味覚や嗅覚に起因する
- フードの鮮度や保存方法の違いが食欲に大きく影響する
- 食感や粒の大きさが合わないと食べづらく、好き嫌いの原因となる
- 過去の不快な体験や新しい食べ物への警戒心が好き嫌いを強める
- 好き嫌いや食欲不振が急であった場合は病気の可能性がある