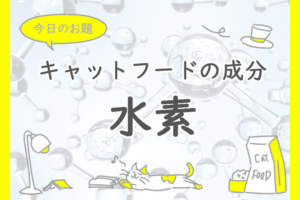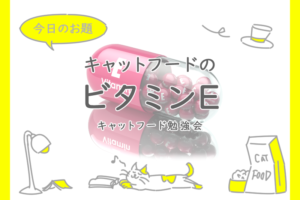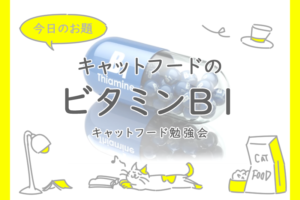目次


低アレルゲン設計のキャットフードとは、猫がアレルギーを起こしやすい食材を避けてつくられた一般食のことです。療法食ほど厳密ではありませんが、日常的にアレルギー対策をしたい飼い主さんに向いていますよ。
似た言葉で「アレルゲン除去食」や「食物アレルギー対応」がありますが、それらとの違いについても解説しますね。
低アレルゲン設計とは
キャットフードのパッケージや商品説明で「低アレルゲン設計」と記載されることがあります。
「低アレルゲン設計」とは、猫が食物アレルギーを起こしやすいとされる食材を避け、比較的リスクの低い原材料を中心に配合していることを意味します。
ただし、「低アレルゲン」という表現には法的な明確な基準はなく、表現や記載はメーカーごとの判断となります。そのため、内容を正しく理解し、飼い主自身がパッケージや成分表を読み取ることが大切です。
低アレルゲン設計キャットフードの特徴とメリット
アレルギー発症のリスクを軽減
食物アレルギーとは特定の食材に含まれるタンパク質などに対して、免疫システムが過敏に反応してしまう状態を指します。皮膚のかゆみや脱毛、消化不良や下痢などの症状があらわれ、猫の快適な生活を妨げる大きな要因となります。
猫の食物アレルギーで報告されやすい食材には以下があります。
- 鶏肉
- 牛肉
- 乳製品
- 魚類(とくにマグロや白身魚)
- 穀類(小麦やトウモロコシなど)
これらを完全に排除するのは難しい場合もありますが、低アレルゲン設計のキャットフードは極力アレルギーの発症リスクを減らすことが期待できます。
消化吸収のサポート
低アレルゲン設計キャットフードは、猫の消化吸収を助け、胃腸が敏感な猫でも栄養を吸収できるよう工夫されています。
以下のタンパク質は、一般的にアレルゲンとなりにくい・消化器に負担をかけにくい特徴を持ち、低アレルゲン設計のキャットフードに使われやすい原材料です。
| タンパク質 | アレルゲンになりにくい理由 |
|---|---|
| 加水分解タンパク質 | タンパク分子を細かく分解し、免疫反応を起こしにくくしたもの。療法食に多い。 |
| ダック(鴨肉) | 鶏肉や牛肉より使用頻度が少なく、比較的リスクが低い |
| ターキー(七面鳥) | 鶏肉よりもアレルゲン報告が少なく、消化性も良い |
| カンガルー肉 | 日本では珍しいが、新奇タンパク源として療法食にも使用 |
| ウサギ肉 | 利用例が少ないため、アレルギー持ち猫の代替タンパク源として採用 |
| ラム | 低アレルゲンとして有名だが、近年は使用増で反応例もあるので注意 |
どんな猫におすすめ?
- 食物アレルギーの症状が疑われるが、確定診断は出ていない猫
- 皮膚トラブルや下痢を繰り返す猫
- 安心できる原材料を選びたいと考える飼い主の猫
ただし、症状が強い場合は自己判断せず、必ず獣医師の診察を受けましょう。
低アレルゲン設計キャットフードの注意点
法的定義がない
「低アレルゲン設計」という言葉には、実は明確な法的基準が存在しません。メーカーごとに判断基準や配合方針が異なるため、ある製品ではチキンを避けている一方で、別の製品では魚類が使われていることもあります。
そのため、単に「低アレルゲン」と書かれていてもすべての猫に安全という保証にはならず、飼い主自身が成分表示を確認する姿勢が欠かせません。
確定診断には不十分
猫にアレルギーの疑いがある場合、本当に原因となる食材を特定するには「除去食試験」が必要です。これは、特定の食材を徹底的に排除した療法食を一定期間与え、症状の変化を観察する方法です。
低アレルゲン設計のキャットフードはあくまで一般的な配慮食であり、診断や治療を目的とした除去食試験には使えません。症状が続く場合は獣医師の診察が必要です。
効果は猫ごとに違う
低アレルゲン設計のキャットフードを与えても、ある猫には効果が見られる一方、別の猫には依然としてアレルギー症状が出ることもあります。これは猫ごとにアレルゲンの種類や体質が異なるためです。
そのため「低アレルゲンだから安心」と思い込み過ぎず、実際に与えたあとの体調変化を丁寧に観察することが大切です。異常が続けば必ず獣医師に相談しましょう。
コストが高め
低アレルゲン設計のキャットフードは、原材料に配慮し特定のタンパク源だけを使用したり、アレルギーリスクの低い新奇タンパク質を取り入れたりと、通常より仕入れや製造にコストがかかります。
そのため、一般的なキャットフードに比べ価格が高めに設定されていることが多いです。
成分表示で確認すべきポイント
原材料名
キャットフードを選ぶ際は、まず第一原材料に注目しましょう。
第一原材料とはそのフードに最も多く含まれている食材のことです。先ほどご紹介したダック(七面鳥)やカンガルー肉などの比較的アレルゲンリスクの低い食材が先頭に書かれていれば、アレルギーに配慮されていると言えます。
反対に、「低アレルゲン設計」と記載があっても牛肉や小麦、乳製品など猫にアレルギーを起こしやすい食材が上位に来ている場合は注意が必要です。
タンパク源の数
成分表示を見ると、複数の動物性タンパク質が混在しているキャットフードもあれば、1種類のみを使用した「シングルプロテイン」のキャットフードもあります。
タンパク質が多いキャットフードは嗜好性が高まる効果がありますが、どの食材がアレルギー発症の原因か特定しづらくなるため、食物アレルギーの原因を特定したい場合や、予防的にリスクを減らしたい場合にはシングルプロテインの方が有効です。
添加物
キャットフードには保存性や見た目を良くするために添加物が使われることがあります。人工着色料や香料、化学的な保存料などは猫の体質によって負担になる可能性があるため注意が必要です。
とくにアレルギー体質の猫には、なるべくシンプルで自然由来の保存料(ビタミンEなど)を使用しているキャットフードを選ぶと安心です。成分表示を見て不必要な添加物がないか確認しましょう。
「アレルゲン除去食」「食物アレルギー対応」との違い
低アレルゲン設計と似た言葉で、「アレルゲン除去食」と「食物アレルギー対応」があります。それぞれは定義や特徴が異なります。
| 低アレルゲン設計 | アレルゲン除去食 | 食物アレルギー対応 | |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | 一般的な市販フード | 市販フード(より配慮型) | 獣医師処方の療法食 |
| 目的 | 発症リスクを下げる予防的配慮 | 敏感体質や疑い例への配慮 | 診断や治療に用いる除去試験 |
| 原材料の特徴 | 牛肉・乳製品・小麦などを避ける | シングルプロテインや特定穀物不使用 | 水分解タンパクや新奇タンパク源を使用 |
| 法的基準 | なし(メーカー独自判断) | なし(メーカー独自判断) | 療法食として厳格な設計 |
| 対象猫 | 健康だがアレルギーが心配な猫 | アレルギー疑いの猫や敏感体質の猫 | アレルギー確定診断や治療が必要な猫 |
| 注意点 | 全ての猫に合うわけではない | 療法食ほど厳密ではない | 獣医師の指導下で使用必須 |
使い分けの目安
- 日常の配慮・予防:低アレルゲン設計
- 疑い例や敏感体質により強い配慮:食物アレルギー対応
- 診断・治療目的、除去食試験:アレルゲン除去食(療法食)
いずれも「合う・合わない」は個体差があります。
アレルギー症状(かゆみ、下痢、嘔吐、脱毛など)が続く場合は、自己判断での切り替えを繰り返すのではなく、獣医師に相談し適切なアレルギー除去食試験を行うことが大切です。
まとめ
- 低アレルゲン設計は猫が反応しやすい食材を避けた一般食
- 法的基準はなく、メーカー独自の判断で表示されている
- アレルゲン除去食は療法食で、治療や診断に用いられる
- 成分表示を確認し、シングルプロテインなどが安心材料
- 全ての猫に適応するわけではなく体調観察が欠かせない