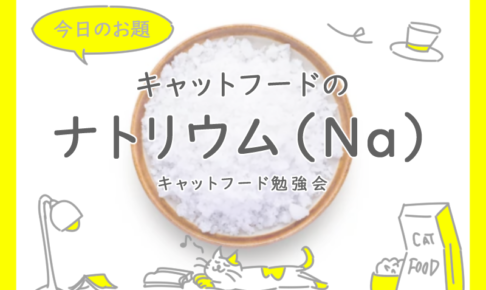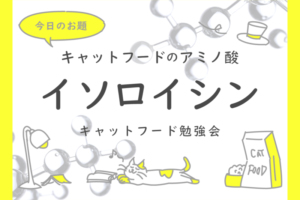目次



はい、療法食を始め、特定の病気や疾患に配慮したキャットフードでも、ミネラルに配慮した製品が多く販売されているので、疑問に感じている方や気になっている方は多いのではないでしょうか。
ということで、今回はキャットフードのミネラルについて紹介していきたいと思います。
キャットフードのミネラル(灰分)とは
ミネラル(灰分:mineral)は五大栄養素のひとつで、無機質や鉱物の性質を持つ必須栄養素の総称です。
キャットフードの成分分析値ではミネラルは灰分と表記されることが多く、ドライフードでは大体7~10%ほどの割合で含まれています。
ミネラルはあらゆる植物や食べ物に含まれますが、それぞれの配合量や他成分とのバランスが重要なので、それぞれ過剰・欠乏にならないよう細かい成分基準が設けられています。
猫におけるミネラルの働き
- 骨や歯などの器官を構成
- 浸透圧、pH、筋収縮、情報伝達の調節に関与
- 酵素やホルモンなどの構成要素
- 酵素やホルモンなど賦活財として生理機能に関与
ミネラルは体内で合成してつくることができないので、食事からバランスよく取り込む必要があります。必須ミネラルが不足すると猫は体の正常な機能を保つことができなくなり、体のいたる所に異常や問題が生じます。
【特に重要】カルシウム:リン:マグネシウムの比率
ミネラルは種類が沢山ありますが、その中でも多量ミネラルであり骨を構成するカルシウム、リン、マグネシウムの3つは、特にバランスと比率が重要と言われています。
AAFCOの基準ではカルシウム:リン=1~2:1とかなり広い範囲が設定されていますが、推奨されている比率はカルシウム:リン:マグネシウム=1.2:1:0.08です。
このバランスが崩れると、十分に吸収されず体外に排出される量が多くなるため、尿路結石や慢性腎臓病の原因になると考えられています。
猫に必要なミネラルの種類
現在、猫の必須ミネラルは24種類であるとされています。
また必須ミネラルは多量ミネラル・微量ミネラルに分かれており、多量ミネラルは体内において一定量の補給が必要になります。
| 必須ミネラル | 働き | 動物体内の濃度 | |
|---|---|---|---|
| 多量ミネラル | カルシウム | 骨や歯を構成 筋肉収縮 神経興奮の抑制 血液凝固作用 細胞分裂 | 15g/kg |
| リン | 骨や歯を構成 DNAやRNAを構成 リン脂質の材料 ATPを構成 pHを調整 | 10g/kg | |
| マグネシウム | 骨や歯を構成 筋肉の収縮 神経伝達 | 0.4g/kg | |
| カリウム | 浸透圧の調整・維持 神経刺激の伝達 心臓・筋肉の調節 酵素反応の調節 血圧の調節 | 2g/kg | |
| ナトリウム | 浸透圧の調整・維持 筋肉収縮や神経伝達 栄養素の九州 | 1.6g/kg | |
| 塩素 | 胃酸を構成 殺菌作用 | 1.1g/kg | |
| 硫黄 | 必須アミノ酸を構成 交感神経の働きの抑制 自律神経の安定 コレステロールの排出を促す | 1.5g/kg | |
| 微量ミネラル | 鉄 | ヘモグロビン(赤血球)を構成 酸素の運搬 | 20~80mg/kg |
| 亜鉛 | ビタミンAの運搬 視覚や粘膜維持 細胞分裂・DNA合成 骨の成長 インスリンの構成維持 | 10~50mg/kg | |
| 銅 | 貧血予防 骨の形成と維持 被毛の色素合成 | 1~5mg/kg | |
| モリブデン | 貧血予防 脳や神経伝達 鉄分の働きを高める | 1~4mg/kg | |
| セレン | 免疫機能の維持 重金属の毒性を軽減 抗酸化作用 | 1~2mg/kg | |
| ヨウ素 | 甲状腺ホルモンを構成 神経伝達 子猫の細胞分化 | 0.3~0.6mg/kg | |
| マンガン | カルシウムの石灰化 生殖機能維持 抗酸化作用促進 | 0.2~0.5mg/kg | |
| コバルト | 0.02~0.1mg/kg | ||
| クロム | - | ||
| ヒ素、鉛、ニッケル、ケイ素、 バナジウム、フッ素、スズ、リチウムなど | - | ||
動物にとってその物質が不足した時に欠乏症が生じ、そのミネラルを補給して欠乏症が治癒すれば必須ミネラルであるという証拠になるので、今後上記以外にも必須ミネラルに物質が加わる可能性もあります。
カルシウム(Ca)
カルシウムは、リンと共に体の骨や歯の材料となる栄養素です。また細胞と細胞の間で情報や神経の伝達にも関わっています。
骨の中に常に蓄えられているので、欠乏することは少ないですが、カルシウムが不足すると骨に蓄積されたカルシウムから補われるため、骨の密度が下がり、骨粗鬆症の原因になったり、骨がもろく骨折やケガをしやすくなります。
カルシウムの過剰摂取は尿路結石を招く原因にもなるので、リンやマグネシウムとのバランスが大切です。
リン(P)
リンは、カルシウムと共に骨や歯、また細胞壁をつくるリン脂質の原材料となる成分で、肉やレバーなどの動物性食品に多く含まれています。
リンは旨味の構成成分でもあるため、リンが豊富な食材を使用すると猫の食いつきも良い傾向になります。
リンの過剰摂取は腎臓に負担をかけるため、腎臓病が進行した猫は低リン食が勧められます。またカルシウムとマグネシウムとのバランスを崩すと下部尿路疾患の原因にもなります。
マグネシウム(Mg)
マグネシウムもまたカルシウムやリンと共に骨や歯を構成する成分で、神経の伝達や筋肉を動かすためにも必要不可欠です。マグネシウムやリンの次に多い多量ミネラルで、海藻や魚の骨に多く含まれています。
マグネシウムは多くても少なくても尿路結石の原因になると考えれており、少なすぎるとシュウ酸カルシウム結石、多すぎるとストルバイト結石になってしまうので、適正範囲内でかつカルシウムとリンとのバランスを考慮して摂取しなければなりません。
ナトリウム(Na)
ナトリウムは必須多量ミネラルのひとつで、体を動かす時の筋肉の動きや、無意識のうちに行われる各器官の働きなど生体が活動するために必要不可欠です。ナトリウムは細胞外液にほとんど含まれています。細胞内にあるカリウムと共に細胞内外の浸透圧の調整を行い、筋肉の収縮や神経の情報伝達、栄養素の吸収や輸送など様々な体の機能を正常に保っているので、ナトリウムとカリウムのバランスが崩れると体に異常が現れます。
また塩分は塩素とナトリウムによって構成されているので、塩分の過剰摂取とはつまりナトリウムの過剰摂取ということになります。
カリウム(K)
カリウムは必須多量ミネラルのひとつで、細胞内液でナトリウムとともに神経伝達や筋肉の収縮、栄養その吸収や輸送などを行っています。果物や野菜など様々なものに含まれていますが、水に溶けやすく、茹でたり煮たりなどの加熱によって失われやすい性質があります。
しかし過剰摂取は尿毒症を引き起こす可能性があるため、キャットフードでも毎日バランスよく摂取する必要があります。
塩素(Cl)
塩素は、遺産を構成する必須ミネラルのひとつで、ナトリウムとともに食塩の構成成分としても知られているかと思います。
塩素が不足することはまれで、むしろ高塩分にならないよう摂取量を控える場合が多いです。
硫黄(S)
硫黄はシステインやメチオニン、タウリンなどを構成する栄養素であり、含硫アミノ酸として摂取できるため、AAFCOの栄養基準では最低基準が定められています。
代わりに含硫アミノ酸の最低基準が設定されているので、通常の食事で硫黄が不足することはまずありません。
鉄(Fe)
鉄分といえば血のイメージが強いと思いますが、実際吸収した鉄分の半分以上が血液中のヘモグロビンとして働き、体全体に酸素を運びます。
鉄分はほうれん草やレバーに多く含まれています。またレバーでなくても、肉類、魚類にも含まれています。
猫の体内で鉄が不足すると、貧血を起こしやすくなり、急に猫がふらついたり息が切れたりといった症状が現れます。猫の食事はタンパク質が多く含まれる肉や魚がメインとなるので、鉄が不足して貧血になるケースが多いです。
普通にキャットフードを与えていて鉄分を過剰に摂取してしまうことは少ないですが、サプリなどで多量の鉄を摂取すると、嘔吐や下痢などの症状を引き起こすことがあります。
亜鉛(Zn)
亜鉛は200以上の酵素の補因子として、タンパク質の合成や細胞の複製、DNAの合成、インスリンの構成やビタミンAの運搬など様々な働きに関与しています。
レバーや牡蠣、肉類に豊富で、欠乏すると皮膚炎や脱毛、成長不良などの障害が見られます。
銅(Cu)
銅は生体内で骨や骨格筋、肝臓、血液などの健康維持のために働きます。
銅は肝臓で銅酵素として、酵素の運搬や酸化還元、電子伝達の代謝を助けており、貧血予防や骨の形成、被毛のメラニン合成などの働きがあります。
モリブデン(Mo)
モリブデンは穀物など植物に豊富なミネラルで、鉄分の働きを高め、貧血を予防したり、脳や神経伝達を正常に保つ働きがあります。
モリブデンは吸収率が高く、必要量も微量であるためか、キャットフードの最低基準は特に定められていません。
セレン(Se)
セレンはマグロやイワシなどの魚介類、レバーや鶏卵などに豊富な栄養素で、セレノシステインとしてタンパク質を構成しています。
適正量の幅が狭いことから量の調整が難しく、魚介類を多く摂取すると、全身脱毛や成長低下などの過剰症を発症する可能性があります。
ヨウ素(I)
ヨウ素はあまり聞き馴染みがないかもしれませんが、主に栄養素からエネルギーを得るための化学反応に関わり、神経の伝達、体毛や皮膚を作り出すための酵素の構成成分、ホルモンなど様々な役割をこなしています。
海藻などに含まれる成分で、ヨウ素が不足すると、食欲不振、発熱などの症状の他、抜け毛が増えたり新しい体毛が作られずに体毛の艶が悪くなります。
反対にヨウ素を過剰に摂取してしまうと、ホルモンを出す甲状腺の病気になるので注意が必要です。
マンガン(Mn)
マンガンは穀類や豆類などの植物原料に豊富に含まれるミネラルです。キャットフードでは硫酸マンガン、マンガンアミノ酸キレート等の化合物が栄養添加物として配合されることもあります。
消化吸収や抗酸化作用を高めたり、骨の形成を助け、生殖機能を正常に保つ働きなどがあります。マンガンは有害な活性酸素から細胞を守る働きがあるとも考えられています。
キャットフードのミネラル成分基準(AAFCO)
AAFCOでは以下のようにミネラルの最低基準が設けられています。
画像引用元:キャットフード成分基準|AAFCO
日本では総合栄養食と表記して販売するためには、AAFCOの乾物ベースの成分基準をクリアしている必要があるので、総合栄養食として販売されている商品については、ミネラルのバランスや含有量が基準を満たしていると証明できます。
| AAFCO成分基準 (ミネラル) | 最低値 幼猫期・成長期 | 最低値 成猫期 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 2.5g | 1.5g | - |
| リン | 2.0g | 1.25g | - |
| カリウム | 1.5g | 1.5g | - |
| ナトリウム | 0.5g | 0.5g | - |
| 塩素 | 0.75g | 0.75g | - |
| マグネシウム | 0.20g | 0.10g | - |
| 鉄 | 20.0mg | 20.0mg | - |
| 亜鉛 | 18.8mg | 18.8mg | - |
| 銅 | 3.75mg | 1.25mg | - |
| セレン | 0.075mg | 0.075mg | - |
| ヨウ素 | 0.45mg | 0.15mg | 2.25mg |
| マンガン | 1.90mg | 1.90mg | - |
まとめ
- 五大栄養素のひとつ
- ミネラルそれぞれに様々な働きがある
ミネラルの量はキャットフードの背面や側面にある成分分析値で確認できますが、上記で紹介したようなミネラルの種類まで記載されていることは少ないです。
ですが最近は、カルシウム、リン、マグネシウム、ナトリウム、また塩分相当量など、飼い主さんとしても気になるミネラル量やバランスが記載されている商品もあります。
他、成分分析値や原材料などの見方は以下の記事をご覧下さい。