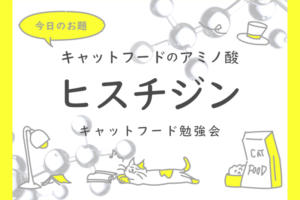目次


確かに人に置き換えてみても、長寿のために毎日同じ味の完全栄養食を食べる人生よりも、世の中の美味しい物をたくさん食べて限りある食事を楽しみたいと考える方が多いのではないでしょうか。


好みがはっきりしている猫や、少食で目安分も食べられない猫、また慢性疾患を発症する猫も増えてきているので、フード選びに関する悩みもよく聞きます。
そういった状況からも今後、愛猫に合わせて食材やレシピを完全にセレクトできる手作りごはんはこれから利用する方が多くなると予想しています。
猫に手作りごはんをつくりたい!

猫の主食として与えるのは市販のキャットフードが一般的ですが、猫の食育や猫の生涯における幸せや充実度(QOL)を考えれば、手作りごはんも是非取り入れていきたいところです。また手作りにすると、ドライフードだけに比べて自然と水分摂取量多くなるので、将来の腎臓猫予防にもおすすめといえます。
すべてを手作りごはんにするのはなかなか難しいところですが、おやつやトッピング、週1~2回の食事をキャットフードから手作りに置き換えるくらいなら、栄養面で大きな影響が出ることはありません。
猫によっては他の物を食べたいと思わない猫もいるので、無理に手作りする必要はありませんが、安心して生活している猫は新しい物に興味を示す傾向があります。もし他の物も食べたがる猫なら、ぜひ愛猫のために手作りごはんにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
手作りごはんのメリット
食材本来のビタミンや酵素を摂取できる
手作りごはんでは鮮度の高い食材を調理してすぐに与えられるため、食材本来の栄養素をたくさん摂取できます。
キャットフードはドライでもウェットでも必ず加熱加工がされており、加熱加工によりビタミンや酵素などは失活して本来の働きが失われてしまいます。キャットフードで最低基準が定められている栄養素はサプリメント(栄養添加物)などでも補うことができますが、AAFCOの基準にない栄養素は得ることができません。
また、キャットフードとして販売する場合、一度にたくさん作って運送や保管などが一定期間行われるので、その間に損失してしまう栄養素も多くあります。
その点、手作りごはんは栄養損失を最小限に抑え、市販のキャットフードでは得られない食材本来の栄養素をたくさん取り入れることができます。
味や食感が変わるので飽き性な猫にぴったり!
さまざまなキャットフードを用意して与えているという方もいますが、ドライフードやウェットフードはそれぞれ食感や風味はどれも似たり寄ったり。
犬と違って猫は好みがはっきりしていることも理由のひとつで、たくさん購入してもらうためには大多数の猫が好む、同じような風味や食感、味付けになりがちです。
しかし手作りごはんであれば愛猫だけが好む食材や風味のものを取り入れたり、食材をカスタマイズしたりできるので、さまざまな味や食感にチャレンジできます。
水分補給と下部尿路疾患の予防にも有効
手作りごはんは自然に水分が摂れるため、下部尿路疾患の予防におすすめです。
猫は水分をあまり取らない傾向があり、それが猫が下部尿路疾患や腎臓病を発症しやすい要因の一つとなっています。手作りごはんではとくに意識しなくても全体の30~80%が水分で構成されるので、意識しなくても猫が水分と栄養を同時に補給できます。
愛猫の体質や病気に合わせられる
手作りごはんでは愛猫の体質や病気に配慮することもできます。
よく聞かれるのが、療法食にすると猫が途端に食べなくなってしまうという相談です。市販フードに戻すわけにもいかず、でも何か食べないと痩せて弱ってしまうという状況のとき、ある成分を抑えつつ、大好きな食材を使った手作りごはんを与える選択肢があると、猫の体力回復や食欲増進に貢献できます。
猫の手作りごはんにおすすめの食材

| 猫の手作りごはんにおすすめな食べ物 | 栄養素 |
|---|---|
| 鶏むね肉 | タンパク質、低脂質 |
| ささみ | タンパク質、低脂質 |
| 鶏ひき肉 | タンパク質、低脂質 |
| 豚肉 | タンパク質、高脂質、ビタミンB |
| 牛肉 | タンパク質、高脂質 |
| 鹿肉 | タンパク質、低脂質 |
| 馬肉 | タンパク質、低脂質 |
| 砂肝 | タンパク質、鉄分、亜鉛 |
| レバー | タンパク質、高脂質、ビタミンA、鉄分 |
| 卵 | タンパク質、卵黄は高脂質、卵白は低脂質 |
| うずらの卵 | タンパク質、高脂質 |
| 鮭(サーモン) | タンパク質、オメガ3 |
| タラ | タンパク質、低脂質 |
| カレイ | タンパク質、低脂質 |
| 鯛 | タンパク質、低脂質 |
| メカジキ | タンパク質、低脂質 |
| トビウオ | タンパク質、リン |
| 猫用かつお節 | タンパク質、塩分 |
| カツオ | タンパク質、オメガ3 |
| マグロ | タンパク質、高脂質、オメガ3 |
| サバ | タンパク質、高脂質、オメガ3 |
| ブリ | タンパク質、高脂質、ビタミンD |
| アジ | タンパク質、オメガ3 |
| イワシ | タンパク質、オメガ3 |
| 桜エビ | タンパク質、オメガ3 |
| ヤギミルク | タンパク質、タウリン、ナイアシン |
| プレーンヨーグルト | タンパク質、高脂質、乳酸菌 |
| オリーブオイル | 脂質、オメガ9 |
| ごま油 | 脂質、オメガ3 |
| 納豆 | 植物性タンパク質、脂質、食物繊維、カルシウム、ビタミンK |
| おから | 食物繊維、植物性タンパク質 |
| 豆乳・豆腐 | 植物性タンパク質、脂質、水分 |
| エンドウ豆 | 食物繊維、植物性タンパク質 |
| サツマイモ | 炭水化物、ビタミンB6、ヤラピン |
| ジャガイモ | 炭水化物、ビタミンB1、カリウム |
| ニンジン | 食物繊維、βカロテン、カリウム |
| トマト | リコピン、ビタミンC、βカロテン |
| キャベツ | 食物繊維、キャベジン |
| ブロッコリー | 食物繊維、ビタミンC |
| カボチャ | 食物繊維、βカロテン、ビタミンC |
| パプリカ | 食物繊維、βカロテン、ビタミンC |
| カブ | 食物繊維、ビタミンC |
| オクラ | 水溶性食物繊維、βカロテン、ビタミンB1 |
| 大根 | 食物繊維、カルシウム、βカロテン |
| 水菜 | 食物繊維、βカロテン、ビタミンC |
| ごま | 食物繊維、セサミン |
| えのき | 食物繊維、ビタミンB1 |
| しいたけ | 食物繊維、エリタデニン、ビタミンD |
| マッシュルーム | 食物繊維、ビタミンB |
| 舞茸 | 食物繊維、ビタミンD、ビタミンB |
| 平茸 | 食物繊維、βグルカン、ビタミンB |
| ひじき | 食物繊維、ヨウ素、ナトリウム |
| バナナ | 食物繊維、カリウム、糖質 |
| クランベリー | 食物繊維、アントシアニン、キナ酸 |
| ブルーベリー | 食物繊維、アントシアニン、ビタミンE |
| リンゴ | 水溶性食物繊維、プロシアニジン、リンゴ酸、クエン酸 |
猫はアミノ酸の旨味を感じ取ることができるので、動物性タンパク質(アミノ酸)が豊富な肉や魚、乳製品は食べてくれやすい傾向があります。また、尿pH値を整えるブルーベリーやクランベリーなどの果物も尿路結石予防に役立つ食材としておすすめです。
ただ猫は好みかそうでないかの判断が厳しく、なんでも喜んで食べてくれるわけではありませんが、意外な物に嗜好性を示すこともあるので、手作りごはんで猫の新たな好物が見えてくるかもしれません。
猫の手作りごはんにNGな食材

| NG・注意が必要な食べ物 | 有害物質 | 症状 |
|---|---|---|
| タマネギ | アリルプロピルジスルフィド (有機チオ硫酸化合物) | 溶血性貧血、ヘモグロビン尿 |
| 長ネギ | アリルプロピルジスルフィド (有機チオ硫酸化合物) | 溶血性貧血、ヘモグロビン尿 |
| ニラ | アリルプロピルジスルフィド (有機チオ硫酸化合物) | 溶血性貧血、ヘモグロビン尿 |
| にんにく | アリルプロピルジスルフィド (有機チオ硫酸化合物) | 溶血性貧血、ヘモグロビン尿 |
| ブドウ | 不明 | 急性腎不全 |
| レーズン | 不明 | 急性腎不全 |
| チョコレート | テオブロミン | 下痢、嘔吐、痙攣 |
| 生のイカ | チアミナーゼ | ビタミンB1欠乏症 |
| 生のタコ | チアミナーゼ | ビタミンB1欠乏症 |
| 生のエビ | チアミナーゼ | ビタミンB1欠乏症 |
| 生のカニ | チアミナーゼ | ビタミンB1欠乏症 |
| 生卵 | アビジン | 皮膚炎、成長不良 |
| コーヒー・お茶 | カフェイン | 下痢、嘔吐、尿失禁、てんかん |
| アボカド | ペルシン | 嘔吐、下痢、うっ血、呼吸困難、痙攣 |
| 海苔 | 塩分、マグネシウム | ストルバイト結石、膀胱炎 |
| 煮干し | 塩分、カルシウム | 高血圧、腎臓に負担 |
| 青魚 | 不飽和脂肪酸 | 黄色脂肪症 |
| ほうれん草 | シュウ酸 | シュウ酸カルシウム結石 |
| 柑橘類 | リモネン(皮) | 手足の震え、嘔吐、皮膚炎、運動障害 |
| 小麦・小麦粉 | グルテン | 腸免疫障害、消化不良、下痢、嘔吐 |
| トウモロコシ | グルテン | 腸免疫障害、消化不良、下痢、嘔吐 |
| 牛乳 | 乳糖 | 腸免疫障害、消化不良、下痢、嘔吐 |
猫に生の魚介類や甲殻類を与えてはいけません。とくに生のエビやカニにはビタミンB1の分解酵素チアミナーゼが多く含まれており、過剰摂取するとビタミンB1欠乏症を引き起こします。チアミナーゼは加熱すると性質が失活するので、猫に与えるときは必ず加熱しましょう。
また、ニラ科の植物もNG食材となります。ニラ、タマネギ、ネギ、ニンニクなどに含まれる有害成分を摂取すると赤血球が破壊され、貧血や血尿などの中毒症状を引き起こします。これらは加熱したとしても性質は失活しません。
青魚に含まれる脂質は酸化しやすく、与えすぎるとイエローファット(黄色脂肪症)を引き起こす可能性があります。給与量を少なめにするか、抗酸化作用のある食材やビタミンEと一緒に摂取しましょう。
グルテン不耐症・グルテンアレルギーの猫の場合は小麦や小麦粉、トウモロコシなどは避け、米粉やジャガイモのでんぷん(馬鈴薯澱粉)などで代用します。
塩や調味料などは猫にとって塩分過剰になるので基本的には使用しません。
手作りごはんのポイント
主成分は動物性タンパク質(肉・魚・卵など)
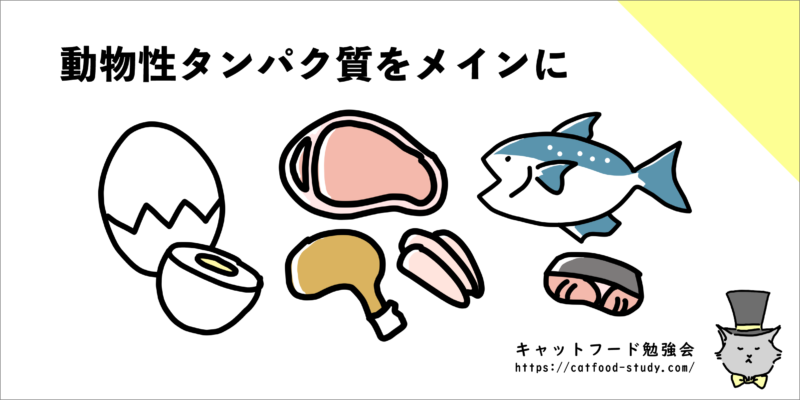
手作りごはんでは、動物性タンパク質がきちんと摂取できるかが大切です。とくに猫は肉食性なので、動物性タンパク質を構成するアミノ酸がより多く必要となります。動物性タンパク質は、肉や魚、卵、乳製品などに多く含まれています。
また、猫は好みがはっきりしているため野菜だけでは食べないこともあります。
そのため、手作りごはんを与えるときは肉や魚などを使用して栄養面と嗜好性をカバーしましょう。
食べやすい大きさと温度を心がける
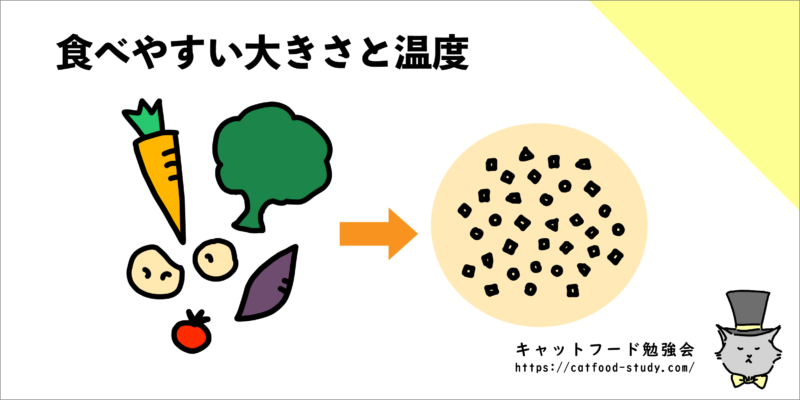
手作りごはんでは、食材の大きさや温度は飼い主さんのさじ加減で決まります。
猫は基本的に丸飲みする動物です。猫は噛みちぎるための切歯は発達していますが、よく噛んですり潰すための臼歯は発達していません。
飲み込める大きさに噛みちぎれればよく噛まずに飲み込んでしまうので、吐き戻しや消化不良が心配な場合はなるべく食べ物は細かくして与えましょう。
また、「猫舌」という言葉があるように、動物に熱々の料理はNGです。加熱した手作りごはんは必ず30~40度ほどに冷まして与えましょう。
年齢・成長段階別で配慮する
◆子猫の手作りごはん
子猫は食物アレルギーを発症しやすいので、早い段階から色々な食材を使うのはおすすめしていません。とくにフルーツは幼齢期にアレルギーを発症しやすいので注意しましょう。
子猫に手作りごはんを与える場合は、猫用ミルクを使ったスープや、これまで食べていたキャットフードに使われている食材を使うようにしましょう。子猫は食べ物をたくさん胃に入れられないので、少量で多くのエネルギーが得られるようカロリーは高めにします。
◆成猫の手作りごはん
成猫は消化器官も成長し体調も安定するので、成猫ならではの注意点はほとんどありません。
さまざまな物が食べられるようになるこの時期はとくに制限はありませんが、何でも与えてOKというわけではありません。NG食材に配慮しつつ、将来の肥満や慢性腎臓病の予防のために低脂質で水分量の多い手作りごはんを与えるのがおすすめです。
◆老猫の手作りごはん
7~11歳位の中高齢の猫の場合、関節炎や運動不足による肥満などが気になってくるので、軟骨やコラーゲンなどが含まれた食材を使ったり、満腹感が得られる低脂質な食事がおすすめです。
12歳以上の高齢猫になると慢性腎臓病などの慢性疾患を患うリスクが高くなるので、食欲低下や体重減少がみられるようであれば、よく食べてくれる嗜好性の高い食べ物やレシピを選ぶのがおすすめです。
慢性疾患は進行すると療法食を与えるようになります。しかし療法食を好まない猫も多く、食べずに衰弱してしまうので、とにかく食べてくれるものへのシフトチェンジ時期がやってきます。
手作りごはんを与えるときの注意点
基本は加熱!火が通っているか確認
最近は生食(BARF)を推奨する方も増えてきていますが、家庭で生肉をそのまま猫に与えるのは食中毒や寄生虫感染のリスクがあるため、おすすめしていません。
手作りごはんで調理を行う場合、加熱では茹でる、煮る、蒸すなど油を使用しない調理方法を採用します。また、香ばしさがアップするので少なめの油で焼く程度なら問題ありません。
揚げる、炒めるなどの方法もありますが、基本的には大量の油を使った炒め物や揚げ物はNGです。
手作りごはんの頻度や回数
手作りごはんの与える頻度は、主食に影響のない量のおやつであれば制限はありませんが、主食として一度に何十グラムも与える場合は、週1~3回くらいまでに留めておきましょう。
もし毎日手作りごはんを与える場合は、しっかりとした栄養計算、総合栄養食と同レベルの栄養を満たせるようなレシピや献立を考える必要があります。
自分で手作りごはんの栄養計算は非常に難しいので、次項でご紹介する手作りごはんのレシピ特化サイトを利用するのがおすすめです。
【おすすめ】猫用手作りごはんの無料レシピサイトを紹介!
犬猫レシピ
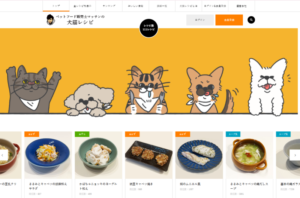
画像引用元:犬猫レシピ 公式サイト

犬猫レシピは、キャットフード勉強会も協賛しているペット用手作りごはんのレシピサイトです。
レシピ作成や監修は愛玩動物飼養管理士・ペット栄誉管理士・犬の栄養管理士が行い、つくったレシピの栄養量やバランス、猫の体重別給与量なども詳細に確認できます。
公開レシピは100以上あり、今日から使える便利で簡単な手作りレシピがたくさん掲載されています。


犬猫レシピが他サイトと異なる一番のポイントは、レシピの信頼性や専門性が高いことです。
たとえば、他サイトやブログでは、猫に与えるのはNGとされるニンニクやアボカドのレシピが掲載されていたり、調味料や塩分が多く使用されていることがあります。給与量も不明確で、どのくらい与えていいのかも分かりません。


一般の方も投稿できるレシピサイトや知識のない方が考案したレシピだと、こういったことがよく起こるのですが、犬猫レシピでは、猫の専門家が責任をもってレシピを考案しているので、安心して利用できます。
当サイトが紹介の手作りキャットフードレシピ
魚をつかった手作りレシピと注意点
鶏肉のつかった手作りレシピと注意点
まとめ
- 当サイトは手作りキャットフード推奨派!
- 愛猫の成長段階や体調、病気、好みなど状態に合わせられる
- 猫用に栄養計算されているレシピサイトも登場している!